ジャン・ジャック・ルソー『学問芸術論』
- 2013.07.02
- 書評

 |
学問芸術論 (岩波文庫 青 623-5) (1968/12/16) ジャン・ジャック・ルソー |
※《》は本書からの抜粋である。
本書『学問芸術論(論説部分)』は、ルソーが1750年のディジョンのアカデミーの懸賞論文「学問と芸術の復興は、習俗の純化に寄与したか、どうかに、について」意見を述べたものであり、またルソーの処女作でもある。短い序文に、学問・芸術と習俗との関係を歴史的に考察した第一部、そして本論と言える、ルソーが生きた”現代”における学問・芸術の復興(今日ではルネサンスと呼ばれる現象)がどのような影響を与えたか、について考察した第二部で構成されている。
第一部では、過去に学問・芸術が栄えた社会において、習俗、特に徳はどうなったかが書かれている。ルソーの論点を要約すると次の通りである。学問・芸術が栄えるにつれ奢侈が増え、肉体は虚弱化し、社会状態の荒廃が生まれる。徳は見せかけの悪徳がはびこり、桎梏(*1)から逃れられず、人は隷属状態に置かれ、頽廃する。では、学問・芸術が栄えていない対照的な社会ではどうだろうか。そこでは肉体の強化が目標とされ、《人は生まれながらにして有徳であり、国土の空気さえ徳を刺戟するように思われる》とルソーは言う。そして勝利をおさめるのは、常に後者であったとも言う。ルソーが念頭において対比しているのが、学問芸術の進んだアテナイと素朴ながら力強いスパルタ、またローマとゲルマン人等である。未開と思われる社会にこそ、真の自由があるという主張は、後の『人間不平等起源論』や『社会契約論』にも引き継がれるいわばルソーの根本テーゼである。
第二部では、学問と芸術の復興が社会に及ぼした影響について述べられている。学問と芸術は無為・悪から生まれ、さらに新たな無為や悪を生み出すという。ここで悪に含まれるのは、時間の浪費、奢侈、習俗の堕落、徳の腐敗などである。だが、ルソーはそうでない真の学問があるともいう。真の学問とは、天賦の才を持った有能な人(例:フランシス・ベーコン、デカルト、ニュートンなど)によってのみ、築かれるべきであり、そうすることにより、徳の学問、素朴な魂の崇高な学問となるという。
今日において、本書を見て、ルソーを批判することは容易い。後のルソーが認める通り、論理的な飛躍はあるし、感情によって書きなぐられたような文章であることは間違いない。またルネサンスが社会に与えた正の影響というものもいくらでも思いつく。だが、そのような断罪はここではやめよう。この作品の現代性などについて、少し触れてみたいと思う。
第一部において、ルソーは、《彼(ソクラテス)は自分の弟子たちやわれわれの子孫への教訓として、彼の徳行の模範と思い出だけを、彼が行ったように残すことでしょう。このようにして、人間を教育することが立派なのです》と述べる。教育の重要性を説く文章でもあるが、それが徳と不可分であること、それはエミールのテーマである。
今日のメディア論を先取りしてるともいえるルソーは文章を残している。印刷術が《人間精神の不条理を永遠化する技術》であり、それにより、《ホッブズやスピノザのような人々の危険な夢想が永久に残る》とも言う。こうしたメディアに対する関心は、ルソーの独創であろう。
このようなルソーの思想の根底にあるのは、現代(近代)人への不信とそれにもかかわらず、将来の人間への期待である。このような考え方は、サンシモン・フーリエ・プルードン・マルクスなどに引き継がれている。また、前者の現代人への不信とまたルソーの現代社会への不信というのは、構造主義をはじめとする、フランスの現代思想にも現れているといえよう。ただし、現代思想の営みは、(ミシェル・フーコーを除いては、)懐疑を抜け出していないように思われる。それは将来に対する不信があるからであろう。構造主義の大家であったC・レヴィ=ストロースがルソーに対して共感を抱くのは、故なきことではないのである。
ルソーはモンテーニュの後に現れたエピステモロジー(*2)の典型人ともいえる。ここでは仔細に立ち入ることはしないが、また別の部分で述べられたらこのテーマは述べたいと思う。
*1 桎梏…自由を奪うもの
*2 エピステモロジー…認識論などと訳されるが、これではなんだかよくわからないと思う。簡単にいうと、ある時代の人が生きる背景に思想があるとすると、その思想の側から学問・科学を批判するという立場がエピステモロジーである。
-
前の記事
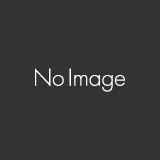
『宗教の見方』人間について考察する際に、人に勧められる本 2013.06.25
-
次の記事
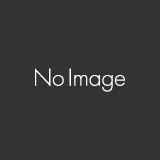
M.Weber『宗教社会学論選』1 『宗教社会学論集 序言』について 2013.07.21